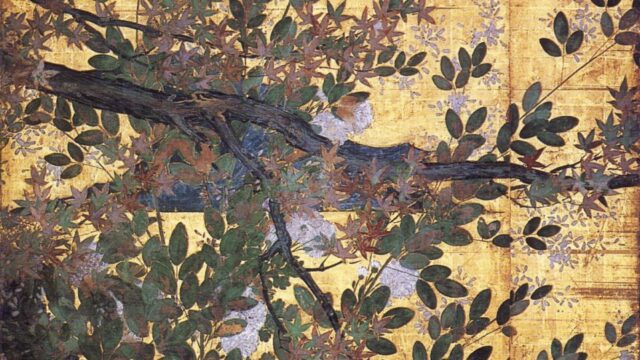「ぬぃの中国文学資料庫」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、唐代の韋応物について、その魅力を紹介していくものになります。韋応物は「王孟韋柳(王維・孟浩然・韋応物・柳宗元)」として、自然描写の詩人とされていますが、実はこの四人はけっこう作風が違ったりします。
韋応物はその中でも、どこか六朝っぽさを帯びているのですが、今回はその六朝らしさを深追いしてみます。というわけで、さっそく本題に入っていきます。
古色あふれる六朝趣味
兵衛たちは鮮やかな戟を並べて、宴席は清らかな香りがみちているので、海上から風雨が至れば、さらさらと池のそばの楼をゆらしました。胸のもたつきも消えて、良き客たちは堂に居並び、わたしはこのような席に入ることを畏れ、また民のことなども想い出すのですが、しだいに是非や進退なども愚かしくなり、ゆたかに肥えた魚はふだん見ないほどのもので、果物も稀にみる艶やかさなのでした。
杯を傾けたかと思うと、また屏の裏がきらきらと騒ぐようだったので、心もふわふわと軽くなって、雨の中の風に巻かれて飛ぶような心地すらするのでした。蘇州あたりには才人が多いので、今日の席はいよいよ賑やかですが、大きな郡に於いては、よろづに付けて何かと華やかでございました。
兵衛森画戟、宴寝凝清香。海上風雨至、逍遥池閣涼。煩疴近消散、嘉賓復満堂。自慙居処崇、未覩斯民康。理會是非遣、性達形迹忘。鮮肥属時禁、蔬果幸見嘗。俯飲一杯酒、仰聆金玉章。神歓體自軽、意欲凌風翔。呉中盛文史、群彦今汪洋。方知大藩地、豈曰財賦疆。(「郡斎雨中與諸文士燕集」)
これは、韋応物の最高傑作のひとつとされているのですが、韋応物らしい魅力がすごく溢れています。
まず、謝朓(六朝の南斉期のひと)がいるのですが、韋応物はとても謝朓らしい句をよく用います(そして、いずれも大きい湿り気の場面だったりします)
たとえば、さっきの「海の上から風雨が来て……(海上風雨至)」は、謝朓の「霧が出て白くもやもやとして(生煙紛漠漠)」「遠くの眺めはどこまでも深くて、庭の下には蒼い林がつづいているのです(曠望極高深、庭際俯喬林)」みたいな句に似ています。
あと、韋応物は「郡斎(郡の官邸)」をすごくよく出しますが(さっきの詩も題名に入っている)、じつは謝朓は官人としての贈答詩がすごくいいので、郡斎がかなり多くでてきます。
さらに、韋応物はよく「東晋~南朝宋のひとに似ている」とされるのですが、その頃は陶淵明・謝霊運の時代です。
陶淵明・謝霊運って、やはり自然描写で有名なのですが、この二人は“流れて止まないこの世の複雑な変化として、山水や自然の美しさがあって……”みたいな雰囲気があります。
さっきのものでは「まるまると肥えた魚は滅多にみられぬもので、果物などもありがたく艶めきをみせていて……(鮮肥属時禁、蔬果幸見嘗)」みたいに、たまたまめぐり会えた複雑な変化――みたいにみえてきませんか……。
あと、韋応物って、どこか古めかしい感じがあるのですが、たとえば「兵衛たちは鮮やかな戟をそびえさせて……(兵衛森画戟)」の「森(木が並んだようにひっそり蒼暗い)」とかが、詩ではすごくめずらしいです。
戟(刃物)が並んだ様子が、つめたい光にあふれていてひっそり蒼暗い……って、少し無理やりなのにすごく似合っていて、一字に無理やり複雑なニュアンスを入れるところが六朝の駢文とかによく似ています(こういう癖のある字は、だいたい先秦の未整理なスタイルに似せています)

でも、韋応物はただ古めかしいだけじゃなくて、「池閣(池のそばの楼)」みたいに、離れたものをするりとつなげたようなときがたまにあるんですよね……(滑らかなのか、がたついているのか分からないみたいな)
ちなみに、謝朓とかだと「この山は百里にわたり、もごもごとして雲と並び、絡まる藤はごたごたとして、曲がった枝はぐねぐねして(兹山亘百里、合沓与雲斉。……交藤荒且蔓,樛枝聳復低)」みたいに、六朝では物がはっきり分かれている感があります(山・雲・絡まる藤・曲がった枝)
なんか、これ一つで延々詳しく長くなりましたが、これだけみても陶淵明・謝霊運・謝朓あたりが混ざっているのがみえます……。
淡泊な五絶
もうひとつ、韋応物は歴代最高の五言絶句がとても多いです(私の中では)
五言絶句は、もともと六朝期の長江あたりの民謡として生まれてきたのですが、植物が豊かで水が多くて、「私」と「あなた」だけの世界――みたいな作風です。
あなたと分かれて以来、なんか毎日うさうさとして、黄蘖(きはだ)がこんなに育ったのに、まだ何をしても楽しくないの――。
自従別郎来、何日不咨嗟。黄蘖鬱成林、當奈苦心多。(『楽府詩集』巻44 子夜歌)
ですが、しだいに六朝後期あたりに文人の五言絶句が出てくると、わずかに湿った雰囲気だったり、どこか官能的な味わいだけをほのめかすような感じになっていきます。
そんな中、韋応物の五言絶句は、かなり本来の五言絶句らしさを残していて、しかも文人らしさもあって……というすごく絶妙なバランスになっています(というわけで、韋応物の五絶です)
柳の葉が池を埋めるように落ちて、朝の霜は高い楼をかこむように白いのでした。連日ずっとうろうろしてますが、あなたと別れてから暇ばかりです。
庭の花がたくさん草の上につもっているのに、花蘇芳だけがいつまでも艶やかな紫で、こんな庭に昔いっしょに遊んだ人を憶うのでした。
柳葉遍寒塘、曉霜凝高閣。累日此流連、別来成寂寞。(「寄盧陟」)
雑英紛已積、含芳独暮春。還如故園樹、忽憶故園人。(「見紫荊花」)
すごく似ていませんか……。五言絶句は、やや湿っていてつやっぽい――みたいなイメージはその頃からあったのですが、俗世の哀楽が濃いところは同じで、しかも文人の場面です。
遠くで江の上の笛がきこえて、そんなときにあなたを送ったのでした。今日はひとりですごす夜ですが、郡邸より笛の音がするようです。
荒れた寺は山の雪をのぞんで、しずかな部屋は竹林にむかっていますので、ここで過ごしながら、どこかあなたの静かさを思い出しました。
遠聴江上笛、臨觴一送君。還愁独宿夜、更向郡斎聞。(「聴江笛送陸侍御」)
野寺望山雪、空斎対竹林。我以養愚地、生君道者心。(「酬令狐司録善福精舍見贈」)
この二つは、謝朓ふうの官人の贈答詩なので、もともとの五言絶句らしさと、さらに郡邸(郡斎)が出てきたりして、謝朓らしさ(官人らしさ)も混ざっています。
ふたつめは、しいていうなら“道人の情”みたいな感じですかね……。ちょっともったりしていて高尚なのか俗縁なのか混ざりあっているような魅力です。
そして、すっきりと澄んでいるようで、どこかしっとりと湿っている自然がつつんでいる……というのが、とても味わい深いのです(この混ざり方が韋応物の良さなのかもです)。もう一つ、すごく好きなものをみていきます。
紅い樹にして花は無く、石のようで瓊(玉)でもなく――、世の人はどこで取ってきたのかと云えば、蓬莱の石の上に生えていたのです。
絳樹無花葉、非石亦非瓊。世人何処得、蓬莱石上生。(「詠珊瑚」)
これは、珊瑚を詠んだものです(中国では、珊瑚は飾り物として好まれました)。実は六朝の民謡でも、これにどこか似ているものがあって、それもすごく魅力的なのです。
うつくしい景陽の山、花のような百尺の楼があって、その上には貴家の人たちが、さらさらと遊んでいるのです。
可憐景陽山、苕苕百尺楼。上有明天子、麟鳳戯中遊。(『楽府詩集』巻49 孟珠)
なんていうか、五言絶句の名品って、遠くのことは何かがあってもぼんやりみえない――みたいなのが、すごくいいんですよね……。
韋応物の五言絶句って、陶淵明・謝霊運っぽさ(自然の多彩さを好むところ)だったり、謝朓っぽさ(官人らしさ)だったり、民謡の五言絶句らしさ(身のまわり数mの私とあなたの世界)みたいなのが、すごく独特の混ざり方になっていて好きなのです。
というわけで、かなり長めの韋応物の記事でしたが、その魅力が少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。お読みいただきありがとうございました。