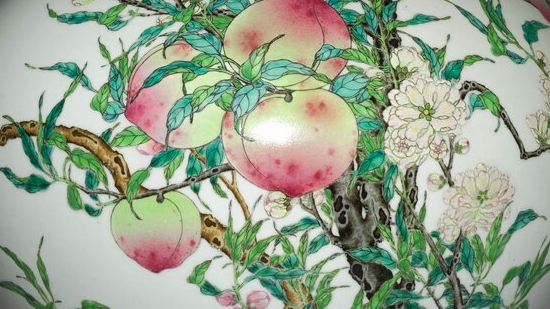「ぬぃの中国文学資料庫」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、清代の袁枚(えんばい)についてです。袁枚はふつう詩で有名なのですが、実は駢文のほうがもっとすごいです(たぶん)
清代の作品って、どれも洗練されていて、いままでの名品を再現するような、優等生ふうの仕上がりになっています。ですが、袁枚の駢文はとても自在で、しかも人を驚かすような字が入っていて、すごく面白いのです。
なので、清代の中でも、いままで見たことがないというか、すごく新しい感じがするので、ぜひ魅力を感じていただきたいと思って紹介してみます。
奇趣繽紛
1751年7月、黄河が河南省にてあふれた。あふれた水は壺を傾けたようにながれて、山東省までくると、川水は馳せ集まって、馬の群れがたまっているようになり、山東の聊城市をぬけて東に行き、北の大清河から海に出ていった。
河の役人たちは毎日やつれながら口々にあれこれを急ぎ片づけていたが、山東省を任されていた史奕昂はひとまず落ち着かせて、「南北に通じる堤をつくり、水をひとつにまとめれば、すべて落ち着くだろう」と云って、黄河を任されていた顧琮総督にも書面を送った。
「山東省聊城市あたりはすでに水の中で、濁った水が高く詰まって、堤も呑まれているので、石を積むこともできず、泥を掻きだすのも、あちらを掃けばこちらに溜まるという状態で、手のつけられないので、西の流れを止めなくては、いつまでも東に溢れつづけるばかりで、家や橋も壊れて、いくつもの湖に囲まれた中にいては、いずれ埋まってしまいます。ここはなるべく早く河南の穴を塞いで、流れを止めて、東に於いて進めたいこととして……」
乾隆十六年夏六月、……黄河決豫州。自陽武建瓴而下、……達斉魯、……川瀆来彙、如馬逸不止。……水穿張秋之掛剣台而東、由大清河入海。……諸河官色変而言哤、……兗沂道史公抑堂止之、下令曰「築南北堤、……水不左右衝、民稍安。」公乃上書総河顧公曰「掛剣口已為江河矣。黄流稽天、堤根茫茫、将焉置土石?欲挑浚者、此刷彼淤、畚鍤無所施。夫上源不断、徒念下流、是屋梁之崩而輔以数祌之支、不缺則敗。……急塞陽武咽喉、既断流、乃従事於東。……」(「史公張秋治河記」)
これ、訳すと全く面白くなくなるので、すごく困るのです……。
まず、すごく上手いなぁ……と思ったところをあげていきます。「川瀆来彙(川の水は馳せ集まって)」の“来彙(来て集まる)”が、小慣れない組合せなのに、実際の様子にすごく似合っています。
あと、水が溜まっているのが「馬の群れがうろうろと溢れているようで(如馬逸不止)」もかなり癖の効いた比喩です。その前にあった「壺を傾けたように流れて(建瓴而下)」とあわせて、初めは水だったのに、いつのまにか馬になって……みたいな奇妙な取り合わせがすごいです。
ちなみに、前漢の賦にすごく似た例があって、笙の音について「もよもよと溢れながら馬が溜まったようになり、さらさらと洩れてまた高まっていくのでした(或漫衍而駱驛兮、沛焉競溢)」みたいにしているところがあります(これが原案かは謎ですが……)
あと、「哤」ってあまり見慣れない字ですが、こういう見慣れない字をいきなり入れるのは先秦~前漢あたりに多いです。尨(ぼう)は「厖大(膨大)」とかと一緒で、ぼやぼやぼてぼてと大きく膨らんだ感じです(ここでは話ぶりがあたふたと落ち着かず、乱れているみたいな)
そして、書面に入ると、もはや解説しきれないほどすごいです。
まず、「江河(水の中)」「茫々(水に呑まれている)」みたいな無理やり雰囲気だけで結びつけている比喩みたいなところがやはり先秦ふうの重々しい奇怪さを帯びています(先秦って、ちょっと未成熟で分かりづらい比喩が多いです)

あと、「此刷彼淤」は、刷:泥を掃く、淤:泥が溜まる、此:こちら、彼:あちらです。こちらを立てればあちらが立たず――の泥ver. みたいなものだと思ってください(こういう一回かぎりの慣用句っぽいものをいきなり作ってくるセンスが凄すぎる)
「西の流れを止めなくては、いつまでも東に溢れつづけてしまい……(上源不断、徒念下流)」も絶妙な崩し方です。上源(上流の源)と下流(下流にむかう)って、きれいな対比になっていそうで、少しずれているけど、源・流れみたいな水系の字だけなので、まとまっているようにも見える……という不思議さです(笑)
いつまでつづくのかと思われそうなので、あと一つだけ紹介すると、袁枚の駢文って、じつはあまり対句が多くありません(駢文は、対句の多い装飾文体です)
ですが、よくみると四文字ずつで意味がきれいに分かれるようになっていて、たとえば「川瀆来彙、如/馬逸不止」「黄流稽天、堤根茫茫、将/焉置土石」みたいに、四文字+あまり意味のない字(如・将など)のセットです(六朝期にはなんとなく四文字ずつセットにしていました)
というわけで、袁枚の駢文って、駢文なのかもしれないけど、対句を並べるというより、先秦ふうの古めかしくやや奇怪な字を入れたり、即興で慣用句みたいなのを出してきたりして、むしろとても不規則なのです。
神力自在
私は南の邸に帰りましたが、あなたは北の宮中に留まり、そのときから分かれて、あなたは階を走りて位を馳せていきましたが、あるときは数日のうちに官省を巡り、もしくは三十年のうちに早くも総督まで兼ねるようになり、一たび浙水に臨みては、二たび蘇州の水門に入りて、南の魚が南から長江に入りて、黄河が東に流れたようで……。
我宰江左、公留燕闕。従此乖分、辵階猟級。或旬日之間而周歴三台、或三十之年而早麾旌節。……一臨浙水、両巡呉門。南鯯湘流、東釃河源。(「祭荘滋圃中丞文」)
さっきの解説が多すぎたので、今回はかなり少なめにしました(でもかなり見どころはあります)
まず、「辵」は、大昔の“しんにょう”なので、進む・辿り着く系です。なので、「辵階猟級」で「位階をつぎつぎ進んでいく――」です(わざと大味な古めかしい字を入れてくる系です)
あと、こちらは荘有恭という人の官歴が、ほとんど浙水(浙江省)・呉門(江蘇省蘇州市あたり)に多かったので、「一たび浙水に臨みては、二たび蘇州の水門に入るようで(一臨浙水、両巡呉門)」みたいになっています。
あえて「……年に――になって」みたいなのじゃなくて、任されていた地域の様子だけを並べるところが、すごくなめらかでいいと思いませんか……。
そのあとの「南鯯湘流、東釃河源」は、とても訳しづらいですが、鯯:南のほうにいる魚、釃:注ぐなので、「南にいる魚(荘有恭は広東省生まれ)は、南から入ってくる川(湘流)で長江下流(浙水・呉門)まできて、それは黄河(河源)が東に流れてくるようで……(東釃)」とかですかね……。
こういうふうに、あえて川系の語彙しか入れない――みたいな縁語は、六朝の駢文でも「滄海のまだ動かぬうちに、魚の私は打ちあげられて――(滄溟未運、波臣自蕩)」とかがあります(中国文学での縁語って、すごく少ないです……。ちなみに、海・魚が縁語です)
というわけで、洗練されているけどやや小さくまとまっている清代駢文において、もっとも異彩を放っている袁枚の駢文についてみてきましたが、最後に袁枚につけられた興味深い評をみてみます。
これは、同じく清代の洪亮吉がつけたもので、袁枚の詩は「神力を得た妖狐が、酔ってその尾をあらわしたような――(如通天神狐、酔即露尾)」というものです笑。
これは詩についてなので、短い詩をひとつみてみます。
人の心が想いを凝らしていると、天上には一片の雲が涌いてきて、高い雲は空から来て、低い雲は足元より出て、高いものは大傘の如く、日を遮ってありがたかったが、低いものはふわふわ遊んで、海の上にひらひら薄くまとっていた。
下の雲たちはさらに下には蜃気楼がもわもわと涌きだして、その上には碧の空がどこまでもつづいていて、どうやら雲上の雲でなくては、真の楽しみは得られないらしい。
人心一念動、天上片雲起。高雲起空中、低雲起脚底。高者若張蓋、遮日殊有情。低者若游戯、鋪海尤分明。俯首看蜃市、仰首謝碧落。倘非雲上雲、安得楽中楽。(「観鋪海時甚苦太陽思有掩覆之者忽然雲生竟得倚松而坐」)
……なんだろう、この独特の間延び感というか、上手なのですが、ちょっと話しているような雰囲気というか、駢文に比べるとややゆるいというか……。
詩の中にでてくる字も、「倘(もし~~)」みたいな現代語ふうの字が入っていたり、「高雲・低雲」みたいにすごくあっさりしています。
さっきの「神力を得た妖狐が……」って、本来はとてつもないセンスと技をもっているはずなのに、やや術が緩んで、甘い仕上がりになっているような詩――ということなのかもです(こちらの雲の詩も、駢文ふうに練り上げれば、たぶんとてつもない素材なのかもです)
もっとも、袁枚は駢文においてはその凄まじい神力を溢れさせて用いているので、袁枚は駢文がすごく魅力的――という話でした(袁枚の駢文は、歴代でも最高級だとおもっています)
すごく分かりづらい話をしてしまいましたが、お読みいただきありがとうございました。