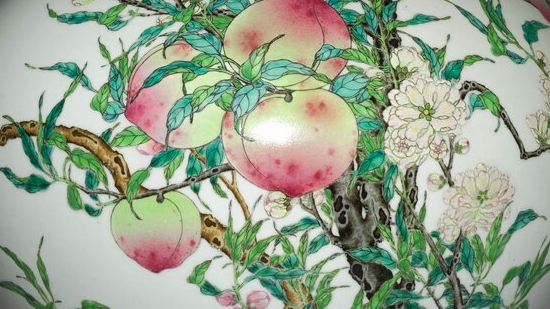「ぬぃの中国文学資料庫」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、清の乾隆帝時代(1735~96)の詩についてになります。乾隆帝時代は、清代の爛熟期とされていて、すごく多彩な詩が魅力的なので、その豊かな個性を感じていただけたら嬉しいです。
ちなみに、乾隆帝時代の詩壇については、同じ頃を生きていた洪亮吉がそのころの有名な作者100人をまとめて批評しているので、今回はその批評とあわせてみていきたいと思います。


紀昀 春光霈々、光怪陸離
まずは、乾隆帝時代でもとりわけ有名な紀昀(きいん)です。
紀昀については「苕霅の水に舟をうかべて、風光は清らかで明るいような――(如泛舟苕霅、風日清華)」と評しています。
これはすごくわかりやすくて、苕(ちょう)・霅(そう)は、どちらも浙江省の川の名です。ゆったりと麗らかにながれる川に舟をうかべて、きらきらと明るい春の陽射しがさしているような……みたいな雰囲気です。
雲母の窓はきらきらとして、道を行く人はまるで鏡の中のようで、七つ曲がりの坂はがたがた険しくて鉄の如く、山の骨はそれでもなぜか水晶のように澄んでいるのでした。
雲母窓櫺片片明、往来人在鏡中行。七盤峻坂頑如鉄、山骨何縁似水精。(紀昀「烏魯木斉雑詩 其七十九」)
これは、ウルムチ(西域)のめずらしい風物を詠んだものなのですが、きらきらと小さい雲母石が散らばっている坂を行けば、その坂はぐねぐね険しくて鉄のように鈍い耀きをおびていて、どうやら山の中には、大きな水晶が眠っているらしい――みたいな感じです。
この「きらきらと明るい耀き感」がすごく紀昀らしいです。どこか潤んだような、ややゆれているような光というか……。もう一つ、ちょっと面白い話がついている詩をみてみます。
潘南田の絵はざらざらと痩せたようで、それでいて冷たく意地の固まったような人だったので、酒を飲むととにかく口が悪くなり、あまり世に受け入れられなかった。
あるとき、私のために梅花の絵をかいてくれたので、私は「水辺の垣根に横たわり、ひっそりと住む人が昔はこの辺りにいたのだが――。その枝はぐねぐねと固まって黒く割れ詰まったようで、華やかさはどこまでも桃の花に劣るのですが」という詩を付しておいた。
この詩はちょっとふざけ半分で付けたのだが、私がのちにウルムチに行って留守になったときに、家の侍女たちはその薄暗さを嫌がって、桃の花を描いたものを飾っていた。
潘南田画有逸気、而性情孤峭、使酒罵座、落落然不合於時。偶為余作梅花横幅、余題一絶曰「水辺籬落影横斜、曾在孤山処士家。只怪樛枝蟠似鉄、風流畢竟譲桃花。」蓋戯之也。後余従軍塞外、侍姬輩嫌其敝黯、竟以桃花一幅易之。(紀昀『閲微草堂筆記』巻十六)
梅の花が「敝黯(敝:ばさばさと荒んでいる、黯:暗い)」というのが、老いた梅の木のわずかな花と、なんとなくざらざらと固い枝が薄暗くもつれている様子っぽくて、水辺の上にのびていて、やや白っぽい春の光をうつしているのが、紀昀らしい濡れた耀きです。
あと、紀昀は、実は怪談集『閲微草堂筆記』ですごく有名なので、ここからは怪談もみていきます(ちなみに、さっきの話も、「この梅の絵は、がさがさと薄暗くて、桃のほうが華やかだが――」という詩をつくったら、本当に桃の花に替えられてしまった……みたいな不思議な話です)
許方という者が、酒を二壺かついで夜路を歩いていたが、疲れたので木の下で休んでいると、月がすごく明るい夜で、遠くにうぅうぅという声がした。そして、ぼんやりと黒い塊のような死霊が茂みの中からでてきて、ぼやぼやと怖ろしげだった。
なので、樹の陰にかくれて、酒壺の背負い棒をかまえていたが、死霊は酒壺のところにくると、大喜びして、蓋をあけて飲みはじめた。一つ飲み終わると、さらに二つめを開けようとしていたが、その口紐を解いたあたりで、ぐってりと倒れてしまった。
酒壺を運んでいた者はとても恨んで、どうやらこの霊は酒を飲むくらいしか技が無いとわかったので、背負い棒でばしばしと叩きはじめた。霊は叩かれているとしだいにべったりつぶれてきて、黒い烟の一かたまりのようになっていった。
もっとも、さらに姿を変えたりするかもしれないとおもって、重ねて百回くらい叩いていたが、その烟は地面にうすくただよって、ぼんやりなくなって、うす墨のような、うす絹のようなふうになって、ぼやぼやと消えてしまった。
死霊とは、人の余った気で、気は少しずつ薄くなっていくので、霊をみた人はいるけれど、神代の死霊というのは聞いたことがない。酒は溜まった気を散らすので、医者は血や汗をめぐらすために酒を用いるというが、この霊はわずかに残っていた気が、酒を飲んで散ってしまい、消えたのだろう。
許方嘗担酒二罌夜行、倦息大樹下。月明如昼、遠聞嗚嗚声、一鬼自叢薄中出、形状可怖。乃避入樹後、持担以自衛。鬼至罌前、躍舞大喜、遽開飲。尽一罌、尚欲開其第二罌。緘甫半啓、已頹然倒矣。許恨甚、且視之似無他技、突挙担撃之、……因連與痛手、漸縦馳委地、化濃烟一聚。恐其変幻、更捶百余。其烟平鋪地面、漸散漸開、痕如淡墨、如軽縠、漸愈散愈薄、以至於無。……鬼、人之余気也。気以漸而消、故……世有見鬼者、而不聞見羲軒以上鬼。……酒散気者也、故医家行血発汗……之薬、皆治以酒。此鬼以僅存之気、而散以満罌之酒、……其消盡也固宜。(紀昀『閲微草堂筆記』巻二)
あまり怖くない怪談(むしろかわいい)ですが、「一かたまりの黒い烟(濃烟一聚)」「その烟は地面にべったりひろがって、しだいに薄くなり、うす墨のような、うす絹のような……(其烟平鋪地面、漸散漸開、痕如淡墨、如軽縠)」とかがすごく光を湛えています。
あと、話の本筋にあまり関係ないのに「月がとても明るくて(月明如昼)」とかが入っているのが、紀昀の好みかもです(『閲微草堂筆記』の文体って、すごく綺麗なんですよね……)
道観(道教の寺)に間借りしている者がいて、狐女と仲良くなって、毎夜会っていたが、突然数日ほど狐女は来なくなってしまった。しばらく経った夜に、簾をあげて狐女は入ってきたので、なぜここ数日来なかったのかを訊いた。
狐女は「最近新しく来た道士が、まわりから仙力を持っていると云われていて、どうやら本当なのかもしれないと思って、しばらく様子をみていたけれど、今夜 鼠に化けて、しのび込んでみてみたら、どうやら傑物ぶっているだけでしたの」と云っていた。
なぜ仙力が無いと分かったのか訊くと、「にせ傑物は、だいたい二つだけで、一つはひっそりとすべてを隠して、何を考えているのかわからせない者――、もう一つはわざわざ変わったことをしてみせて、何か奥があるのかと思わせる者。でも、静かで落ちついているものは人に見せつけるようでは偽物で、変わったことをしているのも、わざわざ人を驚かせているのは偽物ですの。文人にも有名になりたいからと云って、やたら冷ややかで薄ら暗くひねていたり、奇言奇行を目立たせる人がいますけれど、見たことがありますでしょう。この道士はやたら外に喚きましたの――」と見抜いたらしい。
有僦居道観者、與一狐女狎、靡夕不至。忽数日不見、莫測何故。一夜、搴簾含笑入。問其曠隔之由、曰「観中新来一道士、衆目曰仙、慮其或有神術、姑暫避之。今夜化形為小鼠、自壁隙潜窺、直大言欺世者耳、故復来也。」問「何以知其無道力?」曰「偽仙偽仏、技止二端。其一故為静黙、使人不測。其一故為顛狂、使人疑其有所託。然真静黙者、……凡矜持者偽也。真託於顛狂者、……凡張皇者偽也。此如君輩文士、故為名高、或迂僻冷峭、……或縦酒罵座、……同一術耳。此道士張皇甚矣、足知其無能為也。」(紀昀『閲微草堂筆記』巻十一)
怪談なのかね、これ……。かなり意訳しているけど、「冷峭(冷ややかで捻くれている)」「張皇(ハリボテ的ベカベカ感。皇:煌く)」とかが、かなり光というか、水気を帯びていませんか……(あと、話そのものがかなり面白い)
というわけで、紀昀って詩・怪談どちらをみても少し濡れたような光にあふれているのが、なんとなく感じていただけてたら嬉しいです。
趙文哲 巣のあるものはその巣を離れ
つづいては「宮女が山寺にきて、宮中の華やかさを思い出しているような――(如宮人入道、未洗鉛華)」と評されている趙文哲です。
この人は、雲南~四川省西部の一揆を抑えるために数年ほど送りこまれていて、たぶんそのときの雰囲気についてです。というわけで、送りこまれてすぐの時期をみていきます(雲南~四川省は、濛々とした山々が細かく絡みあうような中に、さらさらと多くの川が通っています)
険しい流れをぬけて、また奇怪な山があらわれる。一峰は空を刺すようで、ざくざくと削げて掴まるところもなく、落ちるような大厓のあいだには、虹の橋がかかっていた。しずかな竹の林をみたいと思って、小さい路から仏寺まできてみると、鐘の音が雲にすいこまれて、渓の下に落ちていった。
さらさらと速い流れはどこまでつづいているのかも知れず、木々に止まる痩せ鵜たちは、どこに枯草の巣をつくっているのかも知れず――。しばらく遊んで日が沈み、訪ね歩くのも疲れて帰るのでした。
乍脱一灘険、又逢一峰奇。一峰撑青空、斗絶不可梯。誰於两厓間、飛橋架虹蜺。想見修竹林、微逕通招提。鐘魚戛雲表、声落山下渓。渓流与相応、杳然去何之。借問鸕鶿砦、何処営苗茨。暫游尚無暇、慚愧津梁疲。(趙文哲「明月巌」)
なんて云うか、山寺の幽深な風物も、いまひとつ彩りを欠いているというか、ぼんやりと鈍く曇ってみえる気がします。とくに「渓の流れはさらさらとして、どこまで遠く去るのか知れず(渓流与相応、杳然去何之)」とかが、いかにも儚げで薄暗く濁っています。
あと、「枝に止まる鵜たちに問うてみれば、その荒れ巣はいずこにあるのかもみえず――(借問鸕鶿砦、何処営苗茨)」も、痩せ荒れた山寺を、どこか物足りなく思っていたり、「山中を訪ね歩くのも疲れて……(慚愧津梁疲)」も、薄暗くなって宿房に帰っていく感があります。
もっとも、しだいに西南の山林に馴染んでくると、少しずつ雰囲気が変わっていきます。
西南の山々はがくがくと冷え削がれて、草木もあまり育たぬほどで、家をつくるほどの木を探せば、ひね曲がってまるで伸びておらず。古い雪を凝り詰まらせて、ゆえに木の骨は硬く緊まり、ぎちぎちとねじれて石の隙間から出て、ぐねぐねと縮みながら枝を出している。
九峰山に住むひとは、老いても山に游ぶことが好きで、とりわけ松の姿を好んで、その画は老妙にして澄んで清く――、物は生まれついた美しさがそれぞれあれば、大小を問わずそれぞれ美しく、人に切られることもなく、巌の外に幾百年を隠れて過ごし、日頃からそんな話を聞いていましたが、送られた画をみてみれば、この老いた幹は鉄を裂くほど固くして、巌峰の寒さを纏うようでした。
蛮山気荒寒、草木生意困。遂令棟梁材、亦莫展尺寸。飽経太古雪、其骨故痩健。屈蟠出石罅、鬱然勢自遠。九峰有老樵、老未厭登頓。愛松寫松影、十指掃塵坌。物貴得本性、豈以大小論。不中匠石程、世外許高遯。平生歳寒盟、読画適我願。此筆可屈鉄、庸以勵衰鈍。(趙文哲「倹堂昨上北山見崖石間皆松樹高僅尺許而奇姿鬱蟠如千百年物以素紙寫之勁秀特絶為題一詩」)
この詩はものすごく題名が長いのですが、「昨日 北山に行ってきた人が、巌の間に生えている松が、どれも数十cmほどしかなくて、しかもその姿はぎちぎちぎりぎりと硬く緊まりねじれて千年百年を経ているようだったので、それを描いて送ってくれた」という展開です。
「物にはそれぞれ生まれついた美しさがあって、それは大小を問わずして(物貴得本性、豈以大小論)」とか、「その画の松は、ぎりぎりとして鉄よりも固く、みていると心がしんと澄むようなのでした(此筆可屈鉄、庸以勵衰鈍)」が、とても山寺の澄んで冷たい風物を喜んでいるような気もしてきます……。
もしかすると、洪亮吉の評は、しだいに山寺の趣きに慣れていくような流れも、少し感じていたのかも……みたいに思わせるような、含みのある評にもみえてきます(こういう微妙なニュアンスの比喩が上手い……)
凌廷堪 樹立の茂りにさっと風、雨が流れて、また横雲が
つづいては、凌廷堪(りょうていかん)という人をみていきます。
こちらの人は「濃絵屏風にカタツムリの這い跡がついて、碑の字が苔に埋もれたような(如画壁蝸涎、篆碑蘚蝕)」と評されています。
もはや何がカタツムリなのか謎すぎると思うので、短めのものをみてみます。
玉の如き堤の外には碧がつやつやとして、ひらひらと人や馬をかくして幾重にも流れるようなので、幾たびの好風と夜ごとの雨で、玉川の橋をかくすばかりに長くなりました。
瓊華島外緑迢迢、拂馬迎人柳萬條。幾陣好風連夜雨、鵞黄遮断玉河橋。(凌廷堪「次洪稚存開封寒食日追憶旧游二十首元韻 其四」)
これはたぶんだけど、「幾たびの好風と夜ごとの雨で――(幾陣好風連夜雨)」というのが、目の前をさらさらと春の雨だったり揺らすような風が漂っていき、古いお屋敷が荒れて、濃絵屏風にカタツムリが這っているような……みたいなイメージなのかもです。
そして、実はこういうふうに風雨がさらさらと長い間すぎていくような詩は、降霊術の自動筆記でつくられた作品に多いのです。というわけで、その例をひとつのせてみます。
(もっとも、こちらは降霊術ではなくて、たぶん霊が詠んだ詩というだけですが)
むかし、李又聃が清初の大臣の邸園にいってみると、その廊には二つの詩があった。一つは「颯々たる西風は破れ櫺(窓)から入って、さらさらと秋草が庭を蔽っているので、月の光はくずれた瓦にさしていて、苔ばかりが壁に青く生えているのです」というものだった。
さらに二つめは「きらきらと星がまばらな夜には、天の川をかくす如き雲があり、欄から庭の草などをながめていると、夜明け前の鐘が小さく鳴りました」とあって、その字はぼやぼやと滲み乱れて、変なクセだらけだった。
李又聃先生嘗至宛平相国廃園中、見廊下有詩二首。其一曰「颯颯西風吹破櫺、蕭蕭秋草満空庭。月光穿漏飛簷角、照見莓苔半壁青。」其二曰「耿耿疎星幾点明、銀河時有片雲行。凴闌坐聴譙楼鼓、数到連敲第五声。」墨痕惨淡、殆不類人書。(紀昀『閲微草堂筆記』巻一)
かなり余談ですが、紀昀『閲微草堂筆記』には、降霊術の自動筆記がすごくたくさん出てきます(そして、どれもがとてつもない名文だったりします笑)。あと、「その字はぼやぼやと滲み潰れて(墨痕惨淡)」が、やはり紀昀らしい湿った霧のような光をおびています。
本題にもどると「欄に座って庭の草をながめていると、夜明け前の鐘がなりました(凴闌坐聴譙楼鼓、数到連敲第五声)」みたいな、ぼんやりと同じところをみていると風景だけが流れていって――みたいな感覚が、ずっと佇んでいる霊っぽくないですか……。
長い間の記憶だけが凝り溜まって、さらさらと流れ過ぎていくのが降霊術っぽくて、「幾たびの好風と夜ごとの雨で(幾陣好風連夜雨)」の凌廷堪もすごくそれに似ています。
あと、荒れた庭園の中にあった「苔ばかりが壁に青く生えていて……(照見莓苔半壁青)」は、洪亮吉の云っていた「濃絵屏風にカタツムリの這い跡があって……(如画壁蝸涎)」によく似ています(たぶん、いかにも降霊術っぽい云い回しだよね……みたいな典型句なのかもです)
というわけで、凌廷堪をもう一つみていきます。
泰山の上にはわずかに雲が一塊りで、石にふれてはふわふわと大きく涌いていき、たまたま私の笈の中にも入ってきたので、いずれ霖雨を興すかもしれないと持って帰った。その雲で滴る雨は丹液を練り、室中に出せば山界の如くして、ふわふわとして泰山の香りをおびて、ただの雲ではないのかもしれません――。
泰山之顚雲一縷、触石俄看布寰宇。偶然携取入笈中、留待他年作霖雨。錬将仙液成金丹、高臥不畏衣裳寒。絪縕好応虞庭瑞、莫与閑雲一例看。(凌廷堪「題黄少眉笈雲図小照」)
これ、すごく好き(笑)「数年のうちに霖雨を起こすかもしれず(留待他年作霖雨)」とかが、いかにも降霊術的な世界です♪
あと、「その雨で丹液を練りて、室中に出せば山界の如く(錬将仙液成金丹、高臥不畏衣裳寒)」とかのもはや何が起こっているのかわからない感じも降霊術らしさです。
李芍亭の家で降霊術をしていたら、邱長春(元代の道士)を名のる者が降りてきて、筆がさらさらと動いて、その字は雨をちらしたような自在さだった。
ある人が丹薬のつくり方を訊くと、その霊は「丹薬づくりとは、金石を焼いて錬ることですが、仙書などで云う炉・鍋・鉛・丹は、どれも喩えですから、本当に焼いて錬るわけではありません。術を好む者たちがいろいろ怪しげなことをして、むしろ変な薬を作っていますが、そもそも金石は熱く燥いていて、さらに火で溶かせば、でらでらと煮え上がって、血脈がふくらみ、効果があったように思えますが、本来の気を喰いつくしています故、禍を長く残します。花を育てる人が、硫黄をあげると、真冬でも花を咲かせますが、咲いた後には、その樹ごと枯れてしまいます。どうやら強い熱を入れて、むりやり精華を湧かせていますので、もっている力を吐きつくして死なせてしまうのです」と書いていた。
李芍亭家扶乩、降仙自称邱長春、懸筆而書、疾於風雨、字如顛素之狂草。客或拝求丹方、乩判曰「……丹方是焼煉金石之術也。参同契爐鼎鉛汞、皆是寓名、非言焼煉。方士転相附会、遂貽害無窮。夫金石燥烈、益以火力、亢陽鼓盪、血脈僨張、故筋力似倍加強壮、而消鑠真気、伏禍亦深。観芸花者、培以硫黄、則冒寒吐蕊、然盛開之後、其樹必枯。蓋鬱熱蒸於下、則精華湧於上、涌尽則立槁耳。」(紀昀『閲微草堂筆記』巻九)
人間には窺い知れない何かがあって、よく分からないままさらさらひらひらと奇怪に流れてしまう感じが、さっきのふわふわと流れて何をしているのかわからない雲に似ていませんか……。
というわけで、乾隆帝時代の詩壇の爛熟感をみてきましたが、それぞれ全然味わいが異なっている魅力を少しでも感じていただけたら嬉しいです。
とても長い記事になりましたが、お読みいただきありがとうございました。