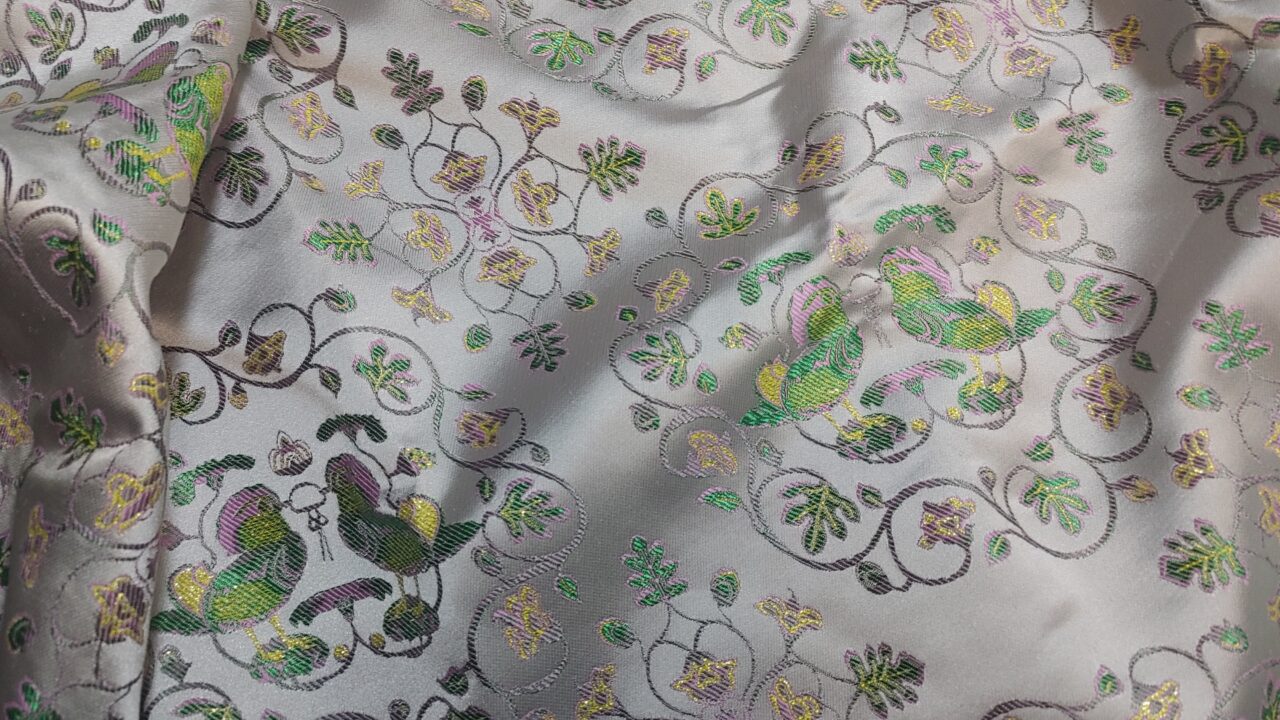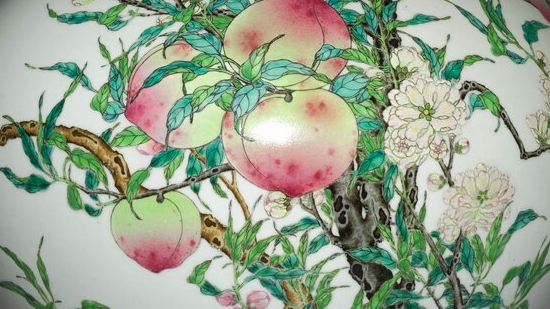「ぬぃの中国文学資料庫」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、清代の洪亮吉(こうりょうきつ)についてです。洪亮吉の五言絶句は、とても内容が独特&複雑で、すごく魅力的なものが多いのです(五言絶句:五字で四句の短い詩)
というわけで、さっそく本題に入っていきます♪
蛟が化けて人に混ざりそうな荒れ芒
まずは、洪亮吉と同じ時期の五言絶句をひとつみてみます。
薄暗いような明けるような、二月のような、秋の紅葉のような色――。ほんのりと青い山のなかで、花が一層の楼に翳りました。
欲暝疑将曙、涼春似早秋。青山独帰処、花暗一層楼。(王采薇「夢中作」)
……この微妙な雰囲気がすごく清代っぽいです。薄暗いような、明るいような、ひんやりと冷たいような、ほんのり霞に濡れているような、青っぽいような、うっすらピンクっぽいような、翳っているような、花が明るいような感じがすごく綺麗です。
清代の詩は、すごく微妙な感覚を繊細に重ねていくことが多くて、しかも五言絶句らしくしっとりと湿ったような質感があります(五言絶句はすごく短いので、半径数mのしっとり濡れた艶めきだけが匂うような含みが大切です……)
ですが、洪亮吉の五言絶句は、かなり様子が異なります。
小さな二階から四方をみてみると、どこまでも茫々たる荒れ野がつづいており、老いた蛟(みずち)は人に化けてきて、たまに戸を叩いたりする――。
一楼四面窓、面面臨曠野。老蛟能変人、時来嚇居者。(洪亮吉「舟行即事 其一」)
……何ですか、これ(すごく素晴らしいと思いませんか)。これだけだと分かりづらいので、ついでにもう一ついきます。
水は天からながれてきたようで、四方の山にあふれて溜まっているようなのでした。四方の山は伏せた釜みたいで、東北の口だけが少し缺けていた。
水如天上来、欲冒四山出。四山如覆釜、東北口微缺。(洪亮吉「過枝陽渡 其二」)
……味わい深い(私だけかもですが)。洪亮吉って、清代ふうの微妙で繊細な感じを入れるのがすごく上手なのはもちろんですが、その感覚がふつうは光や色合いだけなのに、洪亮吉はがさがさばさばさ感だったり、凹み加減だったりと、毎回かなり複雑です。
たとえば一つめの例では、蛟(沼に住んでいる水龍)が夜になると人に化けて家に入ってくることがある――という伝承がある海沿いの村では、いかにも蛟が化けたり隠れたりしそうな荒れ芒ばかりがつづいていて……みたいな、“ぼさぼさがさがさ荒れている様子”というか……。
さらに二つめの例だと、周りを山にかこまれているので、その川は少しずつ溜まって溢れながれていくようで、しかもその山は東北だけが少し低く傾いていそうな――みたいな凹凸感です(ぼさぼさ感・凹凸感だけをみせて、その他の色・明るさはデフォルメして書かないようにしているあたりも、すごくおしゃれ)
というわけで、五言絶句は短いので、いくつかまとめて紹介してみます。
うねうねとして色と色が絡みあって、碧や紫の霧が滴るようにみえるのですが、それは女媧の石が、天の欠けたところを埋めたような色でした。
変わった石は変わった客に会い、風が吹いてさらさらと枯れ葉が舞いました。どうやら百年のうちには、人も石も白く過ぎていくばかりなのですが――。
今年は波風も荒れていて、天の河も白浪ばかりですので、鴛鴦(おしどり)もみんな何処かに飛んでしまいました。
紅い林は千樹ほど――、ある夕にはてらてらと濡れて湿っていますので、山風がさっと来れば、巣に居る鳥たちは頸(くび)を延ばしていました。
五色霞紋好、時看紫翠零。真如女蝸石、一一補天青。
奇石逢奇客、従風亦盪揺。寧知百年外、人共石岧嶤。
今歲風波悪、濤衝星斗辺。鴛鴦三十六、険欲上青天。
紅林千百株、一夕已無影。山風颯然来、巣禽各延頸。
(上から「江行」「山行雑詩 其一」「七夕詞 其一」「長至後一日消寒第一集諸及門餞余洋川書院之生雲閣分賦得山楼即事四首 其四」)
どれもすごくいいです♪まず、一つめは、女媧(中国古代の蛇神)が、天の欠けたところを五色の石を練り固めて塞いだという伝承があって、空の藍紫色を帯びたようなまだらの石の模様だなぁ……みたいな感じです(石のうねうねどろどろと霞がぬめったような混ざり感)
二つめは、山の中に白く痩せたような大きい石があって、それを愛でている客がいて、そんな中をひんやりとした風が吹いていくので、百年ののちには人も石もほっそりと痩せ残っているだけなのかも――という“涸れ感・痩せ感”です。
三つめは、今年の七夕は、大雨ばかりが降っているので、どうやら天上の川もざらざらと荒れてばかりで、鴛鴦たちも逃げてしまうような物暗くてうら淋しい――みたいな暗さ&大荒れ感というか。
最後のは、たぶん巣に居る鳥たちも思わずみてしまうほどの妖しいまでの冷たい紅――とかですかね(「已無影:のっぺりてらてらと濡れている」とかが、なんか妖しげで美しいというか、「山風がさっと吹けば……」がうすら気持ち悪さに惹かれるみたいな)
洪亮吉って、ざらざらした白い石の痩せ感、つやつやつづいている紅葉のうすら冷たい紅、ねばり固めたような模様の混ざり方……みたいに、すごく質感が多彩です。
分類が終わらない
ところで、洪亮吉は、同時代の作者100人を「~~の詩は、……が――しているような」という形で総まとめしています(『北江詩話』巻一にて。ちなみに、百通りの中で使い回しは無いので、すさまじい比喩力です)
その中には、なんとなく雰囲気としてわかりやすいものもあれば、かなり見えづらいところを突いているものもあります。
まずは分かりやすいものでは、紀昀(きいん。怪談集『閲微草堂筆記』で有名)の詩は「穏やかな春の川に舟を浮かべているような(如泛舟苕霅、風日清華)」です。
宴座には蓬莱飾りがあって、石の向こうには仏弟子の像があり、その金光の姿は拝み得ず、わずかに手の平だけがみえており、わたしの描いた絵軸にも、鏡餅の橙かざりなのでした。
宴坐耆闍崛、隔石摩阿難。金容不可睹、得此一掌看。我手何如仏、是画作是観。(紀昀「為伊墨卿題黄癭瓢画冊十二首 仏手柑」)
いかにもきらきらと明るい金光にあふれた宴席が、つやつやとした春の川みたいです。仏手柑は、手みたいな感じでいくつも分かれてのびるタイプの柑橘系で、縁起物として飾られるのですが、それが仏像の手みたいにみえます。

紀昀の詩って、どれも澄んだ光をうっすらまとっていて、ゆったり淡くつづいていく春の川のような穏やかさを帯びています。
ですが、ちょっと分かりづらいものでは「鮑之鍾の詩は、仙境の琵琶がややぎこちなく幽雅な曲を奏でているような(如昆崙琵琶、未除旧習)」「趙文哲の詩は、宮女が山寺に参籠して、宮中の華やかさを思い出しているような(如宮人入道、未洗鉛華)」などがあります。
とりあえず、鮑之鍾をみていきます。
いくつもならぶ山はしだいに尽きてきて、落日が大河にのるように赤くて、水はたびたびあふれるので渡し場を濡らしており、堤は高くて街をやや見下ろすようだったけど、黄楼はぼやぼやたる霧につつまれて、白塔だけがやや見えるので、暮れていく川橋のあたりを、数騎ばかりが入っていきました。
乱山行欲尽、落日大河横。水長頻移渡、隄高半掩城。黄楼迷処所、白塔最分明。暝色沙橋路、弓衣数騎行。(鮑之鍾「晚抵彭城渡河」)
……こちらの鮑之鍾は、洪亮吉と並び称されるほどの詩人だったのですが、なんていうかちょっと鈍い味わいです。とくに「落日が大河にのるように赤くて(落日大河横)」「堤は高くて街をやや見下ろすようなので(隄高半掩城)」あたりが、大味な字をがたがた組合せているというか。
でも全体の雰囲気は、夕闇にぼんやりつつまれていて、すごく綺麗です。たぶんだけど、「仙境の琵琶がややぎこちなく幽雅な曲を奏でている」って、仙境ふうの幽雅さと、どこか古くてぎこちない大味な曲折がついているのが、現代風の滑らかな曲らしくない――とかですかね。
つづいて、趙文哲もみてみます。
また幾たびの梅雨の雨――、金の実たちを樹々につけて、家園の水面に揺られながら、今は大きな湖に出ました。
又是黄梅数番雨、鋳金一点樹同懸。誰知穏住家園日、帯葉分来笠澤船。(趙文哲「薛竹君寫生冊子為賀白儕太守題 枇杷」)
こちらは、果物のビワについてです(なぜか今回は果物ばかり)
まず、「家園の水面に揺られながら、今は大きな湖に出ました(誰知穏住家園日、帯葉分来笠澤船)」って、しだいに遠くの湖に出ていくことを少し悲しんでいるような枇杷の気分です(都を離れた平安貴族みたいなイメージかも)
山寺に参籠している宮女は、ちょっと宮中の華やかさが懐かしいような気がして、ちょっとさびしいような引きずられるような心地――みたいな、何となくのうつろ感というか、薄く沈んでみえる雰囲気に似ています。
(趙文哲は、雲南〜四川省西部の鎮圧で何年もすごしています……)
ちなみに、余談ですが、清代随一の駢文家だった袁枚については、「千年生きている妖狐が、酔ってその尾をあらわしたような(如通天神狐,醉即露尾)」と云っています(駢文では、その神力妖術を漲り溢れさせています)

というわけで、洪亮吉って、なんとなく漂っている繊細な雰囲気を感じるのが、すごく上手いなぁ……みたいな記事でした。かなり狭すぎる話題でしたが、お読みいただきありがとうございました。
2025年10月追記
洪亮吉の同時代評をちょっと詳しくみながら、乾隆帝時代の詩壇について紹介してみました(かなり長いです)